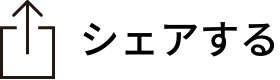入門編・豆知識
食中毒に気を付けて、
お弁当・おにぎりを衛生的に扱うポイント
2025.09.10
-

この記事を監修してくださった方
公益社団法人日本食品衛生協会
公益事業部 技術参与 黒﨑嘉子先生
飲食物が原因となって起こる食中毒などの健康被害を防止し、消費者の健康を守るため、食品等事業者に正しい食品衛生の知識を広めることを目的として、地域の保健所や食品製造業や飲食店等の人々と協力し、 食の安全を守るための活動を行っています。
食中毒に気を付けて、お弁当・おにぎりを衛生的に扱うポイント
夏場は食中毒に気を配ることが多くなります。
お弁当作りの際、食中毒予防に配慮した調理法や、おにぎりを衛生的に握るポイントをご紹介します。
日々のお弁当作りや遠足・運動会の時など、参考にしてみてください。

1. お弁当を安全に持ち運ぶための基本知識
手を介して広がりやすい食中毒原因菌「黄色ブドウ球菌」
お弁当に関係の深い食中毒の原因のひとつに、手を介して広がる代表的な細菌「黄色ブドウ球菌」があります。黄色ブドウ球菌は私たちの日常環境に広く分布し、健常な人の鼻腔、咽頭、腸管等にも生息しており、その保菌率は約40%と認識されています。
また、化膿を引き起こす菌の一つでもあり、手指等の傷口に感染すると菌が増殖しやすいので、包丁による切り傷や火によるやけどなどの手指の傷に注意が必要です。黄色ブドウ球菌による食中毒の多くは、手指を介して食品を汚染することによって発生しています。黄色ブドウ球菌は5~47.8℃の広い温度域で増殖し、10~46℃の温度域で、食中毒を引き起こす原因となる毒素(エンテロキシン)を産生すると報告されています。30~37℃で最も活動が活発になるため夏場は特に注意が必要です。黄色ブドウ球菌自体は熱に強くはないものの、産生される毒素(エンテロトキシン)は熱に強いため、通常の加熱調理では不活化されません。
また黄色ブドウ球菌は塩分耐性があり、食塩濃度 16~18%でも増殖し、他の条件が適当であれば食塩濃度10%でもエンテロトキシンを産生します。食品を例に挙げると、焼き鮭の塩分濃度が、甘口で3%未満、中辛で5%前後、辛口でも10%未満程度とされています。梅干しの塩分濃度は、自宅で梅干しを作る場合は一般的に10~20%程度ですが、食べる際には個人差がありますがかなり塩辛く感じられます。一方で市販の梅干しは5~10%程度の場合が多くみられます。そのため、塩分濃度を高くするという調理法だけで黄色ブドウ球菌による食中毒を予防するには万全とは言えず、まずは菌を食品に付着させないこと、食品中で増やさないことが重要な対策となります。
出典:食品安全委員会 ファクトシート「ブドウ球菌食中毒」を元に加工して作成

調理の鉄則は、菌をつけない・増やさないこと
食中毒予防の第一歩は衛生的な手洗いから人の手はいろいろなことを行うために様々なところに触れています。食事を作るまえには、手指についた食中毒菌やウイルスを洗い落とすために、衛生的な手洗いを行いましょう。
食品を扱う際の注意点
食品に菌をつけないよう手で直接食品に触れないようビニール手袋や食品ラップを用いましょう。調理器具は洗剤できれいに洗って十分乾燥させたものを使用します。野菜や果実、魚介類は流水で良く洗いましょう。肉は食中毒菌が飛び散るので洗ってはいけません。さらに食品の温度管理に気を付けることがポイントです。作り置きはなるべく避けて、ごはんは当日炊いたものを用いる、具材も当日調理するなど、いたみにくい・菌が増殖しにくいよう心掛けましょう。

お弁当を持ち運ぶ際の注意点
細菌は水分のある環境で増殖するため、洗剤できれいに洗い十分に乾いた状態のお弁当箱を用いましょう。ごはんとおかずをお弁当箱の中で仕切っておく、おかずは汁気を良く切っておかず毎にプラスチックカップなどで分ける、生野菜や果物はよく洗い、水気を切ってから別の容器に入れましょう。揚げ物や焼き物など、お弁当には水分がもともと少ないものを利用するとより安全です。調味料は小さな小分け容器で持ち運んで食べる直前にかけるなどが菌の増殖を抑える対策として有効です。
出典:農林水産省「黄色ブドウ球菌(細菌)」を元に加工して作成
出典:農林水産省「お弁当づくりによる食中毒を予防するために」を元に加工して作成
2. 食中毒を防ぐおにぎりの作り方
おにぎりを衛生的に握るにはまず食べる当日に握ります。手洗いを徹底し、水気をふきとり、さらにアルコール消毒液を手にすりこんで手を衛生的に保つと効果的です。そして素手で触らず、ビニール手袋や食品ラップを用いて握ります。また途中で顔や髪などを触らないように注意します。握る時はまずラップにご飯を広げて粗熱をとり、ラップで握って形にしたのちラップを開封して蒸気を逃がして水分を飛ばし、冷めてから包みます。夏場は特に食品がいたみやすく細菌が繁殖しやすくなるため、水分の少ない具材でおにぎりを握ることがおすすめです。ツナマヨ、炊き込みご飯や、混ぜご飯などは水分が多いため夏場は極力控えた方が良いでしょう。また、おにぎりに海苔を巻く場合、ごはんの水分を吸うと海苔についている菌が増えやすくなるため、食べる直前に巻く方が良いでしょう。

3. おにぎりの保存方法と注意点
おにぎりを包んだら、すぐに冷蔵庫に入れて外出するまでの間、冷やしておきます。持ち運ぶ時は、保冷剤と保冷バッグでしっかりと冷たい状態をキープし、日差しを避けて涼しい場所を選んで保管しましょう。時間が経つと菌が増殖するので、なるべく早く食べましょう。
4. おにぎりを握るなど、調理作業に役立つキッチニスタラップシリーズ

キッチニスタラップの特長
おにぎりを握る際、細菌をつけないために有効な食品ラップ。ただしラップの素材によってはフィルムがゴワついて握りにくい場合があります。飲食店やホテルなどの調理作業で日々活用される、しなやかで弾力性のあるキッチニスタラップシリーズは、プロの厨房で最も支持される業務用小巻ラップシェアNo.1※。例えば太巻きをギュッと巻いたり、おにぎりをしっかり握る場面でも、ラップで食材を包みながらも、ラップ越しに食材が指先にフィットするため、素手で握る感覚に近く、衛生面と作業性の両方を確保できます。
出典:富士キメラ総研「2025年 パッケージングマテリアルの現状と将来展望(2024年実績)」

キッチニスタラップ抗菌はラップに付着した細菌の増殖を抑える
飲食店の厨房で広く使われている「キッチニスタラップ抗菌」は、無機抗菌剤の配合により、ラップに付着した細菌の増殖を抑える効果が期待できます(食品に付着した食中毒菌を死滅させる効果を期待することはできません。あくまで衛生管理の補助としてご使用ください)。